『潔癖症たちの憂鬱』
小説 スフィア様
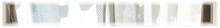
随分と久しぶりの来客は、濡れた前髪を鬱陶しげにぶら下げ俯いたままだった。
どうしたと、そんな言葉が喉を突いたが、すぐに飲み込んだ。
「・・・八戒は・・・?」
ぼそりと独り言の様に呟いた声に、
「ああ、あいつなら、明日まで家開けてるけど」
と、至って普通に答えを返す。金色の髪の先から水の玉が生まれてはポタポタ落ちる様子をただ見ていた。
そして。
ドアを開け放って、どうぞと促すことも帰れと突き放すこともしない。
濡れた法衣が乾くまで、の名目だ。
でも、名目があったって、どうしようもなく不自然なツーショットだ。
コーヒーを作る間も、耳喧しい静寂が辺りを包んだ。
らしくもない訪問。その理由が、気にならなくもなかったのだが。
でもそれはきっとどうでもいいことなのだ。
俺は元来「そこ」に入るためのキーワードを持ち合わせていない。
何も持たないというスタンスが、無意識に染み付いてしまってるんだな。
きっと誰に対してもそうなんだろう。
軽い自己分析をして、そんな自分を小さく笑った。
いくらか冷めたコーヒーを喉の奥へと流し込んで、不意に視線を流す。
仏頂面の男は、さっきから口を閉ざし、コーヒーにも手を付けない。
テーブルに無造作に置かれていた新聞に目を落としたまま、視線は、動かない。
ただ、意識は決してそこにない。
過敏すぎるほど、奴の意識は自分に向けられていた。
心地よいような、微笑ましいような、そんな感情が湧き上がってきて、自分の事ながら驚く。
言葉を促されるのを待ってるのか。
何かのタイミングを見計らっているのか。
生粋の悪戯心に火がついて、奴の思惑を徹底的に無視してやりたい気持ちに駆られる。
けれども。
いつまでもそうやっていられても正直困る。
俺は台詞めいた響きで言葉を吐いた。
「どうかしたのか?」
俺の言葉に。
奴はゆっくり顔を上げた。
未だ湿り気を帯びた金色の髪が顔に張り付いていた。
真っ直ぐすぎるほどに視線がぶつかり、俺は思わず息を呑む。
「・・・に、来たんだ」
それは囁くような小ささだった。だから俺は奴の言葉を聞き逃して。
今何て、と訊く前に奴が動いた。立ち上がる。帰るのかと思ったが違った。
奴は少し離れたソファーに座っていた俺のほうへと歩み寄ってきたのだ。
そして、目前で立ち止まると。
「確かめに、来たんだ」
今度ははっきりとそう言った。
見上げるようなかたちで、俺は奴を見る。
尋常じゃない雰囲気を否が応にも察知していた。
「・・・何を?」
探るように俺は言った。
俺の言葉に応えるように、ギシ、という音が響いた。
奴が俺の座っているソファーに片膝を乗せ、かがむ様にして。
その瞬間、奴の顔が俺の目前で微笑を形作る。
・・・笑った・・・?
「・・・っ」
それから、ゆっくりくちづけられた。
・・・何なんだ一体。
俺は、瞬間、思わず引き剥がそうとする。
しかし、お構いなしのそれに、俺の抵抗もあっけなく萎えて、すぐに違う発想に切り替わった。
俺は、奴の髪に手を差し入れる。そして引き寄せるようにしてさらに深く貪った。
すると、わずかに震えるような反応。
・・・ということは、俺のこの行動は、奴の思惑の範疇外だったのか。だとしたら、肝心なところで分かってない奴だ。
俺はそんなことを考えながら、なおくちづけを続けた。
そして、すっかりなすがままになった身体を、俺はソファーに横たえる。
それから、覆いかぶさるようにして見下げた。
少し息を荒げて、見上げてくる顔。
「俺のちゅーてくでも確かめに来た?」
冗談めかして言葉を吐く癖は自覚している。ひねくれ者だとでも思って諦めて欲しいところだ。
「へたくそ」
赤らめた顔してなにぬかす。・・・少しばかり傷ついたぞ。
奴は憮然とした俺の顔を見ると、喉を震わせるようにして笑った。
不覚にも、少しだけ、見とれた。
それから、ひどく楽しげなその男は、白い腕を、しなやかに俺の首に絡みつけた。
こういうことには、ひどく淡白な奴だと思っていたから、心底意外だ。
けれど、顔見知り程度と言えなくもない希薄な関係だったせいか、奴とこういう行為をする事への抵抗感は無かった。
性別についてもそこまでこだわりのない俺は、ワクワクするような気持ちを抑えられない。
奴の耳の後ろに戯れのキスを落とすと、少しくすぐったそうに顔を振った。
揺れる髪が顔に触れる。
「確かめたいことがあるなら、手伝うけど」
間近にある形のいい耳にそんな言葉を流し入れると、
「随分、面倒見がいいんだな」
と、自分から仕掛けておいて、他人事的な発言が飛び出す。・・・まったく面白い奴だ。
「世界中に愛の手をが俺のテーマ」
「黙れ馬鹿が」
衣服の首元を引っ張られ再度唇が重なった。
きっかけは往々にしてあっけなく忘れられる程度の安易な出来事だ。
色んなきっかけを生み出しては、それを育てることも無くただ腐らせて、日常に埋没していく。
思い知って。
思わず手のひらを押し付ける。両の目に、両の手を。強く強く。でも本当の闇なんかやってこないことを知っている。
お前はいつもそこにいるか。
瞼の裏。
いつかはいなくなるんだろ。
だったら。
何が何でも欲しいという感情は捨てるべきものなのだ。
スローガン。
そして今日という日常。
「お前見計らって来てるだろ」
「何を」
「八戒の留守」
「見られてヤんのが趣味なのか、お前は」
「・・・ヤることしか頭にねーのかよ、クソぼーず」
俺の頭の中にはきっとドでかい寄生虫がいる。
それこそ考えるのが面倒な事情やら理由やら何もかも、全部食べつくす便利な寄生虫。
俺はすっかりどうでもよくなっていた。
目の前にある時間を潰す格好の材料に恵まれただけだった。
今までだってそうやって何もかもを決めていたから、俺が大きく変わってしまったわけでもない。
惰性だらけだ。そんな世界。俺はここから一生出る気はない。
それこそ必死にのたうちまわるのなんて御免なんだ。
・・・ヤることしか頭に無いのは俺か。
「何か言葉を聞かせろ」
こいつは時折変なことを口にする。
ひどく曖昧で意味を理解しかねるような・・・意図的にそう仕組んだ言葉。
俺はまたかとため息をついた。
全く厄介すぎる。顔が綺麗なとこ以外はそれこそ厄介ごとだらけ。
この関係における俺の利点の何と少ないことか。
「むかしむかしあるところに〜」
仕方なく俺がやけくそでそう言うと、
「愛を理解できない、可哀想なかっぱがいました」
俺の続きの言葉を遮るようにして、奴はそう言った。
皮肉めいた笑みを浮かべる目前の男を、俺は別にどうということもなくただ見つめる。
「そのかっぱはエロがっぱだったので〜」
「色んなプレイを嗜みましたとさ」
そう言って、俺は奴をソファーに押し倒した。
さっそくかよ、と喚いたので、お前が言うなと返す。いつもは俺の台詞だ。
首筋に顔を埋める。
ふと、奴が俺の胸のあたりに手をあてた。
「何だよ」
俺はそれを制止と捉えて、少し不満げな声を洩らす。
確かめるようにして。奴はただ黙って自分の手を見つめていた。
何、考えてる。
何かを考えている。
俺には考え及ばないほどに、遠い世界の話を思い浮かべている。
ごまかしや、上辺や、それらを無自覚に振りかざしてみんな生きているはずの世界から離れた。
そんなものだらけの俺の世界とは離れた。
お前は、そういうものとは無縁みたいな面して、そこにいる。
「お前さ」
「・・・何だ」
「何で、俺とセックスすんの」
口を付いて出たのは、何とも馬鹿馬鹿しい問いかけだった。
そんなこと、それこそ俺が俺に訊きたいくらいだ。
・・・あれ。とすると何だ。
俺は、何か理由を探していたのか。・・・いつの間に。
無自覚ゆえの本音か。
・・・何だかむかつくな。
俺は頭の中で勝手に自分に腹を立てながら、それでも奴の言葉を待っていた。
案の定の答えを、待っていた。でないと、何だがひどくバツが悪い。
けれど。
「本当のお前を知りたいからだろ」
さも当たり前に言ってのけた。
何だか、すっげー、むかつくな。
俺は憮然としたまま、奴の言葉をスルーした。
・・・その時から、或いはそもそも最初から。
実は日に日に狂い始めていたこと。
全て把握しきったと思っていた自分という人間の、把握しきれないほどの愚かさを知る。
次へ→