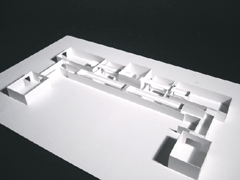クリスタル・パレスからWTCまで
9.11のちょうど150年前の1851年、ロンドンにて第一回万国博覧会が開催された。34カ国が参加し、のべ604万人が訪れたというこの催しは、世界中からものを集め、その名の通り万国の文物を展示しようという最初の試みであった。その会場となったのが「クリスタル・パレス」、水晶宮である。この近代建築史の最初のページに出てくる全長536m、幅124m、高さ30m超の巨大な空間は、産業革命によって大量生産が可能となった鉄とガラスを用いて作り上げられた構造物の最初期の例でもある。
この、あまねく世界中のものを網羅しようという試みは、この時期に世界に対するそのような認識が成立したことを意味する。時おりしも大英帝国がその覇権を地球の隅々まで広げていた時期であり、同国の世界を手中に収めたという実感が、万国博覧会を開催するという発想を導いたことは想像に難くない。国連やオリンピックのように、各国の代表が同等の立場で参加するという今日の万国博覧会のスタイルと、この19世紀の博覧会とではその成り立ちの政治的意味合いがまったく異なるわけである。
万国博覧会は期間が限られた催しであるが、同じく19世紀に美術館や博物館が整備され始めたのも、同じコンセプトによるものだ。イギリスを代表するミュージアム大英博物館は、各国から略奪してきたコレクションによっていることは有名である。エジプトのミイラしかり、アテネの神殿のレリーフしかり。そのようにして世界各地の支配権を得、現地の文化遺産を持ち帰り陳列することにより、その世界制覇の証明する役割が博物館にはあった。であるから博物館とは、純粋に鑑賞や研究のみをその目的とするではなく、その国家の権勢を映し出す装置としても機能した。ここではその後の博物館、美術館の展示空間の変遷を丁寧に追う余裕はないが、その展開の一つの帰結が、ホワイト・キューブと呼ばれる真っ白で四角い空間である。そのニュートラルで特性を持たない場では、空間にディスターブされることなく、どのようなアート作品であっても展示できるとされていて、今日の美術館の展示スペースの一つのスタンダードとされている。
第一万国博覧会の会場であったクリスタル・パレスは、近代建築の夜明けを示すとはいうものの、実際これを設計したのは建築家ではなく造園技師であったというのが通説である。確かにクリスタル・パレスとは、そのまま巨大温室であり、当時発達していた温室を作る技術がそのピークを迎え、それが博覧会の会場として相応しいとして選択されたのであった。実際、蒸気機関や椰子の木など様々なサイズのものの入れものを実現するには、当時開発が進められていた温室の技術しかなかったし、また短期間で建設するという必要に対しても、規格化された鉄骨やガラスを工場で製作し現地では組み立てるだけというプレファブリケーションの方法が適切であった。博覧会会場としての建造物には、いわゆる当時の建築が一般的に持つ様式や装飾は不要であって、ガラスの皮膜でもって大空間を覆うことのみが求められたのであった。この建築が、近代建築の始まりと位置づけられるのは、近代的テクノロジーの初期の成果であるとともに、それまでの文化的伝統から自由になり、「何でも入れられる器」としてあり方がのみ求められたという成り立ちが、その後の時代の建築のあり方を示唆するからである。付け加えるならば、温室のような光あふれる空間は、新しい未来を予感させるにもうってつけであったとも言える。
当時の19世紀にあっては温室というのは新しいビルディングタイプであり、これもヨーロッパ人が世界中で植民地支配を行い、結果もたらされ大量の新しくエキゾチックな植物を入れるための器を必要としていたことに起因する。温室は特にイギリスやドイツなどヨーロッパでも気候が厳しい国々で好まれ、そこには異国への幻想があったわけだが、一方これまで万博や美術館の成立に見たように、自分が征服した世界を収める器が欲しいとの欲望があったことは明白だ。
万国博覧会は今から150年前にはじまり、その後その意味合いを変えながら現在に至るまで続いている。当初は世界中の伝統的でユニークな文化を紹介することにより大いに人気を博するが、それも一回りしてしまうともはや目新しさはなくなり、だんだんと各国の最新の技術や流行の文化を紹介する場となって行く。1925年にはパリで装飾芸術博覧会、通称アール・デコ博開かれるが、この博覧会はそのタイトルの通り、当時のパリやアメリカで最新のモードとしてはやっていたアール・デコを紹介するものであった。このときの主要なパヴィリオンの出品者は、プランタンなどの当時のパリで新しく賑わっていた百貨店であり、この百貨店とはそれまでの小売店とは異なりありとあらゆる商品を扱うという販売方式が人々を惹きつけていた。そして明らかに、この百貨店というコンセプトも、万国博覧会というコンセプトと符合している。
しかし、このパリ博で見過ごせないのは、近代建築最大の巨匠ル・コルビュジェの「エスプリ・ヌーボー館」も出展されていたことである。この典型的なモダニズムのシンプルな箱は、装飾芸術博という当局のコンセプトと真っ向から対立するものであり、出展を一時は拒否され、結局会場の片隅に目立たないように建てられた。コルビュジェは、その前の1914年にドミノという床と細い柱と階段だけで出来た建築のプロトタイプを発表しているが、この床を設ける以外には装飾をはじめとする一切の附属物を排した形式がこれからの建築のあるべき姿であるとした。エスプリ・ヌーボー館は、そのドミノのアイデアを住宅という形で示したものである。(この1925年というのは、クリスタル・パレスの1851年と、9.11の2001年の、ほとんどちょうど真ん中の時期に当たる。)
そして同じく近代建築の巨匠ミース・ファン・デル・ローエは、このドミノを単純に積み重ねたようなビルをアメリカの地で戦後に実現し、単純に床が反復することのみで建物が成立するというビジョンを示し、結果これがいわゆる我々が日常、ビル、ビルと呼んでいる今日世界中の都市で見ることのできるオフィスビルという建物の形式となっている。
アール・デコ博の開かれた1920年代というのは、アメリカの好景気を反映しニューヨークでは超高層ビルが次々と建てられた時期でもあり、都市のスカイラインを大きく変えていた。超高層ビルが出来るには、限られた土地の上で床を無限に反復するという発想が必要であったが、コルビュジェが建築家として理想を提唱するのとは別に、現実的な力学で状況は進んでいたともいえる。ただし、クライスラー・ビルやエンパイヤー・ステイト・ビルなどこの時期の超高層ビルは、アール・デコ風の造形的な頂部や装飾を持ち、それはミースが考えたような単純な四角い箱ではなかった。
1970年には、日本で初めての万国博覧会が大阪で開かれる。ここでメイン会場として計画されたのは、「お祭り広場」という巨大な屋根がかけられたイベント広場であった。もはや収めるものは展示物ではなく、イベントという形を持たない情報となったのだが、ここでもその全体を覆う大きな屋根の下でなにが起きてもそれを許容できるという、そうした仕掛けが作られたのである。展覧会のシンボルともなるモニュメントは、建築物ではなく岡本太郎の「太陽の塔」がその役割を引き受け、その岡本の強烈なインパクトを与えるオブジェは、「お祭り広場」の屋根を突き抜けその下にすべてのものを入れるという建築家の意図を超えた。結局、現在となって万博の跡地にはこの「太陽の塔」のみが残っている。
そして、この万博を軸とし進められたストーリーは9.11に到着する。テロの標的となったWTCは、正方形のフロアーが単純に積層されたビルであり、その頂部は水平に終わっているため、却って終わりがなく永遠に伸びようとしている意志を感じさせる。また、まったく同じビルが二本立っているのも、このビルが無限に反復しうることを示唆しているかのようだ。このビルは、日本であれば畳だとか、イスラムであれば文様だといった、そうした空間の持つ文化的バックグランドを一切排して成立していたが、50カ国以上の異なる国籍を持つ人々が働いていたという。ここでも、ビルは均質空間となり、中で働く人々の人種や文化などを問わない誰でも入ることが出来、やはり「何でも入れられる器」として機能していた。そして、それはアメリカのグローバリズムともパラレルな関係にあり、そのような世界のあり方に違和感を覚えた人々が強く「NO!」といったのが、9.11となった。
メタ・ホワイト・キューブ
今回の展覧会にあたっては、私の役回りは通常の展覧会の会場構成ではないことは、打合せのごく最初から明白であった。アーティストの作品をうまく見せるために、間仕切りや照明を手ごろにデザインするだけではやりがいがないし、そもそも今回はその展示すべきアーティストの作品も事前にはなく、また椿さんがこちらのお膳立ての中でおとなしくしていてくれるとも思えなかった。諸事情により準備時間は極端に短く、アーティストが展示内容を決めるのと同時もしくはそれに先行して、私が建築家として参加できる方法を模索する必要があった。しかしその当初から椿さんは戦争や国連といった、幾分物騒且つタイムリーなモチーフを掲げられ、キュレーターの森さんからはホワイト・キューブと対峙したいという意志を告げられた。具体的なものは見えていなかったが、今回の展覧会のテーマはその最初から非常に明快かつシリアスなものであり、それらに対して、私がどのように向かい合えるかを考えた末の結論が、この「何でも入れられる器批判」である。
以上の考察より、クリスタル・パレスとWTCの痕跡のギャラリー内への設置を提案した。ギャラリー設計者である磯崎新の空間ホワイト・キューブに、もうひとつ「なんでも入れられる器」を挿入することで、メタ・ホワイト・キューブといったコンディションを作り出す。それが、私のこの展覧会への貢献となった。また、後日椿さんから「教室」というテーマも現れ、それもまた「人々を均質に飼いならす装置」として、私の「何でも入れられる器」批判を、補強してもらうものとなった。この現在の世界の困難な状況に対して、応答する機会をいただき感謝している。


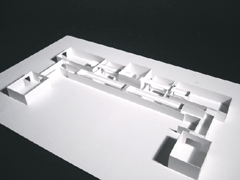
(注記:このテキストは2003年3月23日から6月8日にかけて、水戸芸術館現代美術ギャラリーにて開催された<椿昇「国連少年」展>開催を記念して発行された、カタログ兼アーティストブックに初出された。このたび、関係者の承諾をいただき、ここに再録するものとした。)