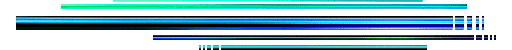
探偵物語.4
能力組織
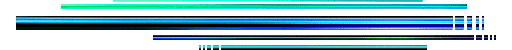
前編
「秘密は守るんだろうな」
それが第一声だった。
「もちろんです」
俺は、できるだけ自信たっぷりに言ってみせた。
重厚なマホガニーの机の向こうには、髪の白くなった男が座っている。それが社長だと紹介されたばかりだ。
六十代後半だろうが、声に張りがある。体の厚みも、脂肪よりも筋肉ではないかと思わせる体格だ。
机の両側に男が一人ずつ立っている。左の男は、口元が社長に似ている。
右の男は、感情がないような目で俺を見ている。俺をここに呼んだ男だ。会社
の名は大友興業。男の名は池井。一階のオフィスを見たところ、芸能プロダクションのようだったが、それは見せかけでしかなく、やばい社会に属する組織であることはすぐにわかった。
社長室はビルの二階にあった。外界の音は完全に遮断されている。かすかに、エアコンの音だけが聞こえている。
社長はじっと俺の目を見た。俺も目をそらさずに見返す。
左に立っていた男が口を挟んだ。
「こんな男に頼まなくても、俺がちゃんと調べますよ」
社長は、男に目をやって、
「わしの決めたことだ」
とだけ言った。
「でも、お父さん」
「ここでは社長と呼べ」
声は低いが、有無を言わせぬ響きがあった。息子らしい男は黙った。
俺の後ろには、濃紺のスーツを着た男が三人も立っている。そろってサングラスをかけているが、サングラス越しの視線が俺の背中に注がれているのを感じる。
「ところで、ご依頼の内容は」
俺は、そう尋ねながら、心の中では「やっかいなことにならなければいいが」
と思っていた。暴力団の依頼は受けないとは言えないし、かといって、話を聞いた上で断ることは許されないだろう。
「まあ、座ってくれ」
社長のその言葉で、秘書らしい若い女がキャスターつきの椅子を押してきた。オフィス・チェアーながら、肘掛けつきのものだ。
分厚い絨毯が敷きつめてあるので、音もなく椅子が来た。
俺は秘書に軽く頭を下げ、深く腰を下ろした。
「二人だけで話がしたい」
俺の後ろでドアの開く音がした。後ろにいた三人が外に出たらしい。右にいた男と秘書も、一礼して出ていった。
「お前もだ」
社長は、左に立っている男に言った。
「でも」
「この男と二人だけで話がしたい」
男は唇をかみ、俺を横目でにらみながら出ていった。
俺は、社長の了解を得てから、メモ帳を取り出した。
「身内に敵が混じっている。それを探り出して欲しい」
俺は視線をメモ帳から社長に移した。
「それなら、私のような外部の者に依頼なさらない方がよろしいのでは」
正直なところ、俺は帰りたくなっていた。
「そういうわけにはいかん。調べろと命じた相手が、その敵かもしれないのだ」
そこで言葉を切り、社長は俺の顔を見た。俺は何も言わなかった。
「こんなことで社内の空気を乱したくないしな。若い者が浮き足だつと、ろくなことにならん。疑心暗鬼になってしまっては、簡単な仕事もうまくいかなくなる。組織というのはそういうものだ」
俺はまだ、断る口実を探していた。社長は俺の心を読んだらしい。
「心配するな。調べさせておいて口封じ、などということはしない。約束しよう。警察に踏み込まれるようなことは極力避けなくてはならない」
警察という言葉を聞いて、俺は細目の刑事を思いだした。あの刑事の世話にはなりたくない。
「ただ、秘密は守ってもらわなくてはならん」
「ご安心下さい。秘密は厳守いたします」
俺の言葉を聞いて、社長は事情を話し始めた。
最近、書類の紛失事故が続いている。
離れたところにある事務所へ、社員が書類を持っていくと、違う書類にすり替わっていたりする。誰かが、仕事がうまくいかないように仕組んでいるらしい。
しかも、それを仕組んでいるのは末端ではなく、上層部の人間と思われる。
「目星はついているのでは」
俺がそう言うと、社長は頷いた。
「怪しいのは、二人いる。一人は、この男だ」
そう言って、社長は机の引き出しから大きめの封筒を取り出し、俺の方に差し出した。
受け取って中を見ると、さっき右に立っていた男の写真と、履歴書のコピーが入っていた。名は池井武。四十五歳。
「もう十年もこの会社にいるが、どうも信用できんところがある」
「この人が何かたくらんでいるとしたら、どういうことでしょう。自分の会社の仕事の邪魔をするには、それなりの理由があるはずですが」
「それがよくわからん」
「ライバル社の指図とか、社内の対立とか」
「ライバル社などあるものか。うちがつぶれて、その分もうかるところなどありはしない。社内の対立はあるが、自分の会社がつぶれてしまっては、生活ができんだろう」
それはそうだ。今のご時世で再就職は容易ではあるまい。
池井はいつも、一階のオフィスにいるという。部長ではあるが、個室はない。
営業室という部屋で、五人の部下と一緒にいるということだった。
俺は気になっていたことを尋ねた。
「さきほど、社員が書類を運ぶということでしたが、いつも同じ人が運んでいますか」
社長は首を振った。
「誰が運んでも同じだ」
「バイク便などに頼んでみては」
「それなことをしていては経費がかかる。社員が自分で運ぶのが一番安上がりだ」
しかも、電車で運べば時間もかからないという。こういう業界の人間はいつも黒塗りの車を乗り回しているのかと思っていたが、そうでもないらしい。
「怪しいのは二人、というお話でしたが、もう一人は」
俺がそう尋ねると、社長は無言で封筒をもう一つ取り出した。
受け取って中を見えると、左に立っていた男、すなわち、社長の息子の写真と住所氏名の書いてある紙が入っていた。名は大友守男。三十四歳。
俺が社長の顔を見ると、社長は小さく頷いた。
「驚くのも無理はないが、怪しいところはあるのだ」
依頼の内容はほぼ飲み込めたが、どうやって探りを入れればいいかは、皆目見当がつかなかった。
「お話はわかりましたが、こうして探偵が呼ばれたということはばれてるわけですから、敵もしっぽを見せないのではないでしょうか」
「そうだろうな」
「そうなりますと、どうも、私の手には……」
「ここまで聞いて断るのか」
「いや、できるだけのことは致しますが……」
そこで社長はにやりと笑った。
「心配することはない。策は考えてある」
そう言って身を乗り出したが、俺はそれを手で制し、立ち上がってそばへ行った。そして小声でこう言った。
「この部屋が盗聴されているおそれがあるのでは」
社長はそれを聞いて感心したようだった。そして、自分も小声で、
「そうだな。屋上で話すことにしよう」
と言うと、立ち上がった。
廊下には誰もいなかった。人払いするとなると徹底するらしい。
俺と社長はエレベーターで最上階へ行き、階段を上って屋上に出た。
外では、開襟シャツの若い男が、柵にもたれてたばこを吸っていた。社長の姿を見て、あわててたばこをもみ消して階段を下りていった。
外では、残暑をかかえたままの空が、うす灰色になって町を覆っている。
部屋の中では聞こえなかった大通りの交通音が、はるか下から耳に届く。
社長は、屋上への出口を見るようにして柵にもたれ、話し始めた。
「わざと書類をほかの営業所に持っていかせることにする。重要書類だと言ってな。その書類が、この会社を出てから、向こうに届くまで、見張ってもらいたい
。途中で何かしてくるのがいれば、それでしっぽをつかめるだろう」
「なるほど。おとり作戦ですね。しかし、重要書類だということになると、社員の方も注意するでしょうから、そう簡単に敵が手を出せないのでは。こちらの社員は優秀な方がそろっているようですから」
「かといって、探偵として顔が割れてるお前さんに頼むわけにもいかんだろう」
「配達業者に頼みますか」
「業者に記録が残るのは困る。特に、むこうの事務所の住所が記録に残ると、警察の手が入った時にやっかいだ」
その時、俺の脳裏にあいつらの顔が浮かんだ。
「どうでしょう。私に心当たりがありまして。頼りにならないこと請け合いの何でも屋がおるんですが、そいつらに運ばせてみては」
「そいつら、というと何人もいるのか」
「はい、三人組です」
「記録は残らないのだろうな」
「もちろん。そんなちゃんとした業者ではありません。ちょっと金を見せれば、たいていこのことはやります」
「そうか。では、頼んでみようか。あとでその何でも屋の連絡先を教えてくれ。
うまくいくといいがな」
「全く。しかし、敵がはっきりしたらどうなさるおつもりですか」
「排除する。いや、なに、体を痛めつけるようなことはせんよ。合法的にやらんとな」
「もし仮に、犯人が息子さんだったとしても」
「容赦はしない。身を守るためには非情にもなる、それが組織というものなのだよ」
二日後、聞き間違えようのない、特徴のある声が電話をしてきた。
「仕事を頼みたいんですが」
「何だ、健子ちゃん」
「いやだなあ、今は三宅ですよ」
「同じじゃないか」
「健子は仕事の時だけです。仕事を頼みたいんですよ」
「つけの取り立てはできないよ。探偵の業務じゃないからね」
「そんなんじゃありません。ボディーガードです」
「一番俺に向いてない仕事だな」
「そう言わないでお願いしますよ。これから事務所に行ってかまいませんか」
「ああ、ちょうど今日は暇だ」
「今日だけ暇なんですか」
「うるせえな。とっとと来い。一人で来るのか」
「三人でいきます」
三十分後、三人がそろって俺の事務所を訪れた。
「ああー、気持ちいい!」
入ってくるなり、森田はそう言ってソファーに寝そべった。
「ほんま涼しいな。やっぱ、クーラーないとつらいな」
そう言って、岡田ももう一つのソファーに寝そべった。
三宅は、
「涼しいね」
と言って、俺の机の方の椅子に座った。
俺はコーヒーを入れていたので立っていた。これでは座るところがない。
「仕事の話で来たんだろう。ちゃんと座れよ」
少し声を荒げてみせると、三人はおとなしくソファーに並んで座った。
俺は、いれ立てのコーヒーをカップに注ぎ、ソーサーに載せて三人の前に並べた。
俺は砂糖は入れないので、客用にスティックの砂糖が用意してある。それを出し、冷蔵庫からクリームも出してやった。仕事の依頼ということなのだから、それなりのもてなしをしなくてはならない。
「あとは?」
岡田が間抜けな声を出した。
「あと、とは何だ」
「コーヒーときたら、ショートケーキやろ」
「クッキーでもいいよ」
森田までもが、調子に乗ってそんなことを言った。
「俺のコーヒーはな、そんじょそこらのコーヒーとは違うんだ。飲ませてもらえるだけありがたいと思え」
三人はおもしろくなさそうな顔で、コーヒーをすすった。
「まあまあやな」
相手が依頼人でなければ、はり倒すところだ。
俺はぐっとこらえて、三宅に尋ねた。
「ボディーガードと言っていたな」
そのとたん、三人の顔がこわばった。
「そうなんです」
三宅が代表して答えた。
「誰のボディーガードだ」
「俺たちです」
「お前ら? 冗談じゃない。お前らみたいな連中をねらう奴がこの世にいるわけはないだろう」
俺には、どういうことかほとんど読めていたが、わざとそう尋ねた。
「どういうことだ」
「実は、うちの会社で、配達の仕事を請け負ったんですけど、やばいみたいなんです」
「何の配達だ」
「中身はわかりません。絶対に中を見ないで届けろという依頼で。書類らしいんですけど」
「で」
「どうも、やばい組織の取り引きらしいんです」
「断ればいいだろう」
「今さら断れませんよ。引き受けちゃったんだから」
横から森田が口を挟んだ。
「だからやめた方がいいって言っただろう」
「剛は、あの時はなんにも言わなかったじゃないか」
「いや、心の中では、やめておけって言ってた。俺の心の声を聞かないのが悪い」
岡田も口を開いた。
「いまさら仲間割れしてもしゃあないやろ。俺らのこの世での最後の仕事になるかもな」
三人は黙って目を落とした。
俺は少し優しい声を出して尋ねた。
「いつ運ぶんだ」
「明日です」
三宅がまた代表して答える。
「俺がお前たちを護ることはできない。ただ一緒にくっついて行って、やばそうなら教えてやる。それだけでいいか」
「はい」
「で、俺の報酬は」
「一万円でどうでしょう」
「そうだな……。お前たちはその仕事をいくらで請け負ったんだ」
「三万円です」
俺は少し考えた。
普通なら、書類を運ぶだけで三万円などという仕事は断るだろう。
しかし、仕事と金がないことにかけては天下有数のこいつらは、後先考えずに引き受けてしまったらしい。引き受けた後で怖くなって俺のところに来たわけだ。
しかし、その中の一万円で、俺にすがろうというところは少しかわいくもあった。
「いいだろう。引き受けよう。支払いは前金だ。いいな」
三人は顔を見合わせ、それからそろって頷いた。
翌日の午後、俺は大友興業のビルの前の喫茶店で、コーヒーを飲んでいた。三人より早く来て、窓際の席で様子をうかがっていたのだ。
コーヒーを少しずつすすりながら玄関を見ていた。安っぽいブレンドだった。
特に香りが死んでいる。俺に任せれば、もっと香りが引き立つようにするのに。
三人がビルに入り、すぐに出てきた。誰かが後をつけている様子はない。
金を払って外に出ると、予想外の男に声をかけられた。
「探偵、何してるんだ、こんなところで」
井ノ原刑事が立っている。なんでこいつがここにいるんだ。
「いや、なに、この店のコーヒーがおいしいって評判なもんで。特に香りがいいんですよ。おすすめですよ」
「そうかあ」
俺は、刑事が喫茶店をのぞき込んでいるうちに逃げだした。
「人を見たら泥棒と思え」という言葉があるが、まさにそういう心境だった。
俺は、電車のドアにもたれ、サングラス越しに、連結部際の椅子に並んで座っている三人の様子を見ていた。三人とも、顔がこわばっている。
真ん中に座っている森田は、膝の上の黒いバッグを抱きしめていた。さっき、大友興業のビルで渡されたものだ。中に書類が入っているはずだ。
バッグの大きさや、森田の様子から判断すると、ほかに重いものが入っていたりはしないらしい。
両脇の三宅と岡田は、落ち着かない様子で乗客の顔を見回している。
ビルを出た三人は、時折メモをみながら、駅へ行き、環状線を東西に貫く路線に乗って西へ向かった。乗り込む前も後も、誰かが注目しているような気配はなかった。
二十五分後、六つ目の駅で、電車が速度を落とし始めると、三人は席を立ち、俺が立っているドアの反対側のドアの前に立った。
俺は車内の様子を見たが、三人に注意を向けているものはなかった。
通路の真ん中に立ち、左右の車両に目をやったが、こちらを見ている者はいない。
電車が止まり、三人はホームに降り立った。
この駅は改札は一つしかない。
俺は早足で三人を追い越し、周りに気を配りながら改札に向かった。
先に改札をでて、駅の近くの案内図を見ているふりをしながら、三人が改札を抜けるのを待った。ほかに十人ほど改札を通ったが、誰も三人には目もくれない。
三人は寄り添ってメモをのぞき込み、駅前の通りを横切り、駅の正面のビルの裏に回った。
裏には飲み屋が並んでいたが、まだ昼前なのでどれもしまっていた。
俺は用意してきた地図を広げ、道を探すふりをした。
三人は、あるやきとり屋の横の階段を上って行った。その建物は、一階がやきとり屋で、二階から上はオフィスになっているようだった。
俺は三人が見えなくなってから、足音を殺してその階段を上った。
階段を上りきる前に、男の声がした。
「確かに受け取った。ご苦労だったな」
「ありがとうございました」
礼を言ったのは森田の声だった。三人の足音が聞こえたので、俺は慌てて階段を下り、建物から離れた。
三人は明るい表情で階段を下りてきた。岡田が俺に気づいて手を振ったが、俺は素知らぬふりをした。バカな奴だ。誰が見ているかわからないのに。
俺は先に駅に戻り、改札を抜けてホームで待っていた。すぐに三人が現れた。
ちょうどその時、電車が来たので、俺と三人は、違うドアから乗り込んだ。
次の駅をすぎてから、俺は三人のところへ行った。
「無事に済んだようだな」
「終わりました」
三宅の声は明るかった。
「届け先はどんな部屋だった」
「相手は廊下で待ってました。俺たちを見て、向こうから声をかけてきました」
「届けたっていう証拠は、何かもらってきたのか」
「荷物を渡したら、どこかに電話して確認してました。それで終わりです」
「ああ、腹が減った」
岡田が空腹に耐えられない、というような声を出した。
「坂本さん、なんか、おごってえな。これで一万なんやから、なんもせんで手に入れたようなもんやろ」
外に目を向けたまま、森田がつぶやいた。
「寿司食いてえなあ」
人の気も知らないで気楽なやつだら。しかしまあ、書類の運搬過程を見張るのは、大友社長に受けた依頼に含まれている。一つの仕事で二カ所から金をもらうのも気が引ける。
「よし、おごってやろう。ただし、回転寿司。皿は絵のついてないのだけだぞ」
三人はそろって俺に手を合わせた。かわいいもんだ。
(2003.6.6up 後編へ続く)
「探偵物語」目次 |
 メインヘ |